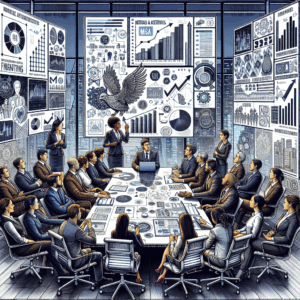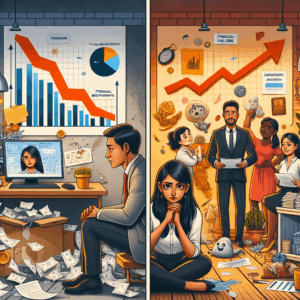こんにちは。創業支援のアドバイザーとして全国の経営者と関わってきた中で、最も多く受ける質問のひとつが「役員報酬」についてです。特に起業したばかりの方々は「いくらにすべきか」「変更するタイミングは?」と悩まれます。私自身、バーチャルオフィスの調査で訪れた数百社の経営者からも、この話題は常に上がっていました。今回は、そんな現場の声を踏まえながら、役員報酬の決定方法について実践的にお伝えします。
役員報酬とは?まずは基本を押さえましょう
役員報酬とは、単なる「給料」ではありません。企業の役員としての責任と貢献に対して支払われる対価です。一般社員の給与とは性質が異なり、企業の命運を左右する重要な経営判断の一つなのです。
ある若手起業家の方はこう話していました。「最初は給料感覚で役員報酬を決めていましたが、税理士さんから『それは違いますよ』と指摘されました。経営判断としての役員報酬の重要性を知り、考え方が変わりました」
役員報酬が高すぎると企業の資金繰りを圧迫し、低すぎると優秀な人材の確保が難しくなります。例えば、私が支援した小売業のA社では、創業時に役員報酬を低く抑えすぎたため、共同創業者が生活の不安から退任するという事態に至りました。適切なバランスが重要なのです。
役員報酬の決定方法-実践的アプローチ
「じゃあ、具体的にどう決めればいいの?」とよく聞かれます。ポイントは3つです。
1. 自社の財務状況を正確に把握する
まずは「使える金額」を知ることが出発点です。例えば、創業期のIT企業B社では「未来の成長期待で今は高めの報酬を」と考えていましたが、実際の資金繰りを詳細に分析したところ、その余裕がないことが判明。無理な報酬設定は避け、代わりに株式報酬も組み合わせる形に切り替えました。
私が大切にしているのは「3年先までのキャッシュフロー予測」です。特に初めて役員報酬を決める場合、「今月は大丈夫」だけではなく、少し先の資金繰りも含めて検討してください。銀行融資の審査でも必ず見られるポイントです。
2. 役員の貢献度と責任範囲を明確にする
「同じ役員でも全員が同じ報酬」は、実はモチベーション低下の原因になりがちです。ある建築関連の会社では、営業担当役員と管理担当役員の報酬を同額にしていましたが、会社への貢献度の差が大きく、不満が生まれていました。
重要なのは、「この役員はどんな価値を会社にもたらしているか」という視点です。例えば「新規事業の立ち上げ」「重要顧客との関係構築」「財務基盤の強化」など、具体的な貢献領域を評価しましょう。私自身、クライアント企業への助言では「役員の責任と成果を数値化する」ことをお勧めしています。
3. 業界相場を参考にする
「うちだけ特別に高い・低い」は避けるべきです。業界団体のデータや、国税庁の「民間給与実態統計調査」などを参考にすると良いでしょう。
例えば、ある飲食店チェーンの創業者は「同業他社より30%高い報酬を設定していた」ことが税務調査で指摘されました。適正範囲を超える報酬は「過大役員報酬」として否認されるリスクがあります。とはいえ、必要以上に低く抑える必要もありません。相場を知った上で、±20%程度の範囲内で自社の状況に合わせて調整するのが現実的です。
業界別・企業規模別の役員報酬相場
「具体的な金額を知りたい」というご要望をよくいただきます。もちろん一概には言えませんが、私が調査してきた中での目安をお伝えします。
実際に私がコンサルティングした東北の製造業C社では、「うちは田舎だから都会の相場より安くていい」と考えていました。しかし、近隣の同業他社と比較したところ、むしろ低すぎる設定であることが判明。社長は「これでは優秀な人材が流出するリスクがある」と気づき、報酬を見直しました。
地域による差はありますが、あまりに低い報酬設定は「この会社は成長していない」というシグナルにもなります。地域相場を踏まえつつも、企業としての成長意欲が伝わる報酬設定を心がけましょう。
ただし、専門分野や経営環境によって大きく異なりますので、一概には言えません。例えば、スタートアップであれば創業期は報酬を抑え、代わりに株式やストックオプションを組み合わせるケースも多くあります。
役員報酬決定時の注意点-税務・法務のリスクを避ける
「税務調査で指摘された」というケースは意外と多いんです。ここは押さえておきたいポイントです。
1. 税務上の最大のポイント「定期同額給与の原則」
役員報酬は、基本的に事業年度の途中で変更できません。これを「定期同額給与の原則」と言います。ある不動産会社D社では、業績好調を理由に役員報酬を年度途中で引き上げたところ、税務調査で指摘され、増額分は「賞与」として扱われ、経費にできなくなりました。
3月決算の会社であれば、通常は毎年6月末までに決定した報酬額を、翌年の6月末まで変更できないと覚えておくといいでしょう。例外もありますが、基本的にはこのルールを守るのが安全です。
私がいつもアドバイスしているのは「年度が変わる前に、次年度の報酬について検討を始める」ということ。直前になって慌てると、十分な検討ができません。
2. 高すぎる報酬には要注意
「社長の報酬は自分で決められるから、いくらでもいい」と考えるのは危険です。相場から著しく乖離した高額報酬は「過大役員報酬」として否認されるリスクがあります。
東京のIT企業E社では、創業者が「自分のアイデアと労力で会社が成り立っている」として、売上の大半を役員報酬にしていました。しかし税務調査で「同業他社の3倍以上の報酬は不相当」と判断され、一部が損金不算入となり、追徴課税を受けました。
客観的に説明できる根拠を持っておくことが大切です。「なぜこの金額なのか」を説明できる資料(業界データや同業他社の事例など)を用意しておきましょう。
3. 社会保険料の影響も考慮する
役員報酬を決める際は、単純な手取り額だけでなく、社会保険料負担も考慮する必要があります。報酬が上がれば社会保険料も比例して上がります。
例えば、月額報酬を90万円から100万円に上げた場合、手取り増加分よりも社会保険料の増加分が大きくなることもあります。福利厚生や退職後の年金を含めた総合的なメリット・デメリットを検討しましょう。
役員報酬の変更手続き—最適なタイミングとステップ
「報酬を変えたい時、どうすればいいの?」というご質問も多いです。
最適なタイミングは「決算期後の定時株主総会」
3月決算の会社であれば、6月の定時株主総会で次期の役員報酬を決定するのが一般的です。この時期に決めておけば、定期同額給与の原則に則った安全な方法となります。
私がいつも経営者に伝えているのは「3月頃から次年度の報酬について検討を始める」ということ。決算見込みや次年度の事業計画を踏まえて、適切な報酬額を事前に考えておくのがベストです。
どうしても年度途中で変更したい場合の例外
「絶対に変更できないの?」という質問もよくいただきます。例外的に、次の場合は年度途中での変更が認められます。
- 事前確定届出給与: 株主総会等の決議から1ヶ月以内に税務署に届け出れば、将来の日付での変更が可能です。
- 業績連動給与: 利益等の業績指標と連動する報酬であれば、事前に算定方法を定めておくことで対応できます。
- 経営不振による減額: 会社の業績が著しく悪化した場合は、報酬の減額が認められることがあります。
ただし、これらの例外適用にはそれぞれ厳格な条件があります。事前に税理士に相談することを強くお勧めします。
役員報酬に関するよくある質問
最後に、経営者からよく受ける質問にお答えします。
Q1: 役員報酬と役員賞与の違いは何ですか?
役員報酬は毎月定期的に支払われる「定期同額給与」であるのに対し、役員賞与は臨時的に支給される一時金です。税務上、役員報酬は法人税の損金(経費)になりますが、役員賞与は原則として損金になりません。
実際にあるメーカーF社では、税理士の指導なしに「ボーナス」として役員に支給していたところ、税務調査で「これは役員賞与であり、損金算入できない」と指摘を受けました。適切な処理方法を知っていれば防げたミスです。
Q2: 個人事業主から法人成りした場合の報酬設定は?
これは本当によく聞かれる質問です。個人事業時代の所得をそのまま役員報酬にしたいと考える方が多いのですが、それが必ずしも最適とは限りません。
私がサポートした飲食店G社のオーナーは、個人事業時代に年間800万円の所得がありました。法人成り後、同じ金額を役員報酬にしようとしましたが、資金繰りを考慮した結果、当初は月50万円(年間600万円)に設定し、会社の内部留保を増やしていくことにしました。結果として2年後には事業拡大の資金が確保でき、新店舗をオープンできました。
最初から高い報酬を設定するより、会社の成長に合わせて段階的に引き上げていく方が、長期的には賢明な場合が多いです。
Q3: 役員報酬を0円にすることはできますか?
法律上は可能ですが、長期間無報酬が続くと、税務上も「不自然」と見なされるリスクがあります。また、社会保険や将来の年金にも影響しますので、慎重な判断が必要です。
ある創業間もないIT企業H社では、資金繰りのため代表が無報酬で経営していましたが、生活費は「貸付金」として会社から借り入れていました。これは税務調査で「実質的な役員報酬ではないか」と指摘を受け、追徴課税のリスクが生じました。
最低限の生活費を報酬として設定し、残りは会社に残すという判断が、多くの場合は安全です。
まとめ:適切な役員報酬が会社の成長を支える
役員報酬の決定は、単なる「いくらもらうか」という問題ではなく、会社の成長戦略そのものです。高すぎず、低すぎず、適切なバランスを取ることが重要です。
- 会社の財務状況を正確に把握する
- 役員の貢献度と責任範囲を明確にする
- 業界相場を参考にする
- 税務・法務上のリスクを避ける
- 適切なタイミングで変更手続きを行う
この5つのポイントを押さえれば、役員報酬の悩みも解決に近づくはずです。私自身、数百社の経営者と関わってきましたが、役員報酬の決定プロセスが明確な会社ほど、経営が安定していると感じています。
最後に一言。役員報酬は「会社と経営者の関係性」を表すものです。会社の成長と経営者の貢献、そして将来への投資のバランスを考えることで、持続可能な経営の基盤を作りましょう。皆さんの会社が、適切な役員報酬によって、さらなる成長を遂げることを願っています。
参考URL: